危険!老化を招く糖化現象とは!?糖化を防ぐ5つの習慣

老化の原因と聞いて活性酸素などによる酸化がまず思い浮かびます
西洋式の食生活がもたらされ多種多様な食文化が食卓を飾るように
食べることは、人生の楽しみのひとつです。
糖化とは、
細胞などを劣化させてしまい、これが進むとAGE(
肌でいうとシワやくすみ、シミや張りが奪われ、
身体の中で作られたAGE(糖化最終生成物)は、
その結果、全身の老化も進行させてしまいます。
「AGE(糖化最終生成物)」とは、例えば、
ホットケーキ

人の身体の16%がたんぱく質でできています。
筋肉や骨、
人体のあらゆる部位を作る上でたん
人体のあらゆる部位を作る上でたん
一方、人のエネルギー源である糖も必要不可欠です。
つまり、
適度に糖を摂取し、それを代謝している分には問題ありません。
骨の3分の1はたんぱく質で出来ており、AGEが骨にたまれば、
神経障害や網膜症、
さらに糖化は脳にも影響を与えると指摘されています。以前から、
アルツハイマー型認知症の患者は、
認知症は、脳の糖尿病と呼ばれることもあるほどで、
糖化が進みAGEがたまっていくと、組織が硬くなったり、
では、どのように糖化ケアを行えばいいのか。
私達は、食事をすることで血糖値を上げ、
食後に起きる「血糖値スパイク」と呼ばれる血糖値の急激な上昇です。
そこで、糖化を防ぐ5つの習慣を紹介します。
1.食事の習慣

間食に食べるお菓子や清涼飲料、
ついつい間食が増えて過食になったり、
食品添加物の甘味料は、
生活習慣病のリスクを考えて食品を選ぶことが大切です。
生活習慣病のリスクを考えて食品を選ぶことが大切です。
お酒の摂取も控えめにすることを心掛けたいところです。
このアセトアルデヒドとたんぱく質が結合することによっても、

「まごわやさしい」とは、
「ま」=豆類、納豆や豆腐など
「ご」=ごま、アーモンド、栗、
「わ」=わかめ、ひじき、昆布、
「さ」=魚(特に小型の青背魚類)いわしなど もしくは良質のオメガ3系の脂質
「し」=
「い」=芋類、
「まごわやさしい」を意識した献立や食材選びをして、普段の食事を見直し、
身体に悪いものと決めてしまうのではなく、

2.食べる順番の習慣

食べる順番は、「ベジタブル・ファースト」
ご飯や、お肉、
ことで後から食べる糖質が小腸で吸収されるのを遅らせ、
野菜の代わりに柑橘系のジュース、レモン水、
また、食事の前にプレーンの植物性ヨーグルトも効果的です。
胃から小腸に移動する時間を遅廷する働きがあり、
コントロールしてくれます。

3.調理方法の習慣
調理方法も糖質ケアにつながります。高温であればあるほど、
一番AGEが少なくて済むのは、
「茹でる」で、次は「蒸す」、
糖質ケアに注意するのであれば、加熱しなく
ても良いような生で食べられるものは生で食べ、焼き物、
4.睡眠の習慣

ライフスタイルの変化に伴い、
しかし、寝不足によってインスリンの分泌が滞ると、
お風呂にゆっくり入ってリラックスし、
5.運動の習慣

アメリカの研究では、食後30分から1時間ほど経った後、
食後30分から1時間というのは、
糖の70%は、筋肉で消費されますので、
できれば、
美容と健康のため、

私たちは、食べたものを消化して体が作られています。
この機会に、ご自分の糖化具合をチェックしてみましょう。
断食美人
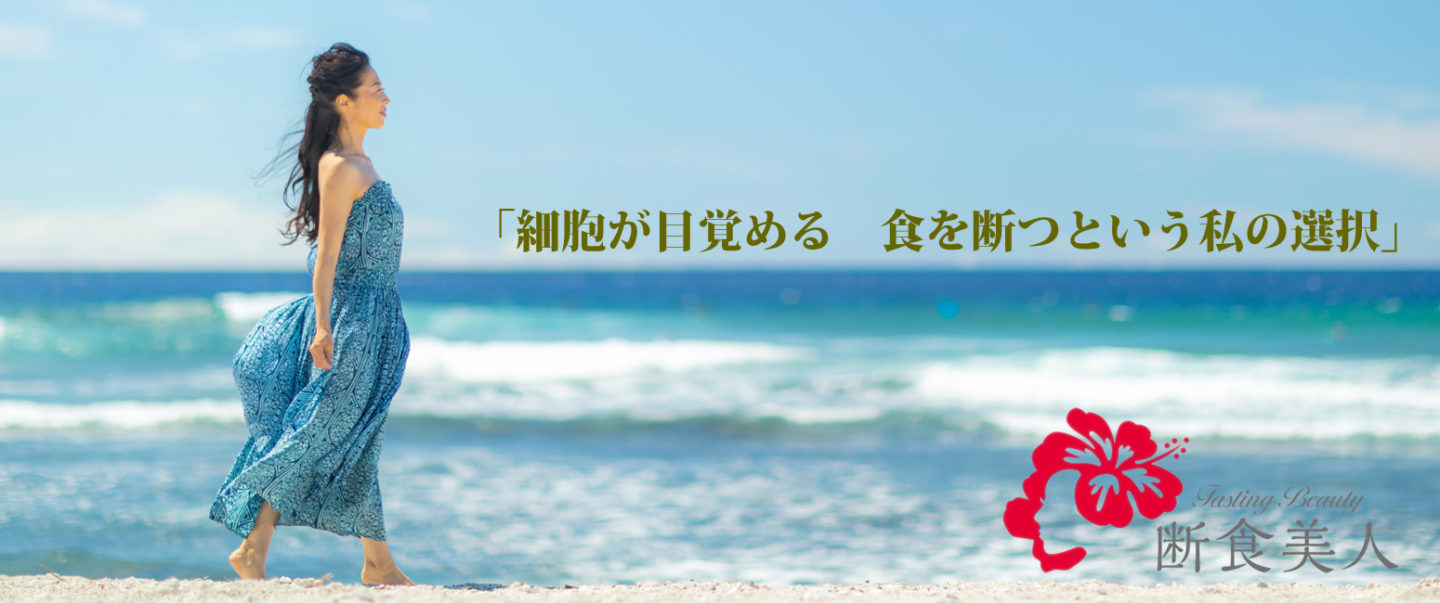

コメントを残す